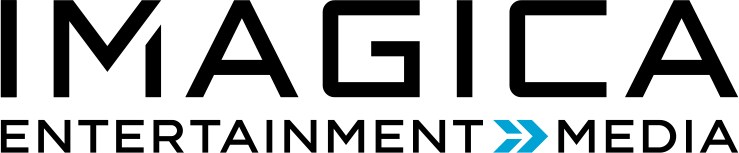映画『この子は邪悪』の世界観をつくる“色”の秘訣

2022年9月1日に公開となった『この子は邪悪』。
“予想外のストーリー、想定外のラスト”が話題を呼んでいる本作の独特の世界観を映像化したのが、カメラマンの花村也寸志氏や照明の永田英則氏らによる撮影チームと、それを支えたカラリストの山下哲司(株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス)。
今回は花村氏と山下が、本作の制作にまつわるエピソードや、世界観をつくり上げるための光と色のコントロールの秘訣を語る。
【あらすじ】
かつて一家で交通事故に遭い、心に傷を負った少女・窪花。
心理療法室を営む父・司朗は脚に障がいが残り、母・繭子は植物状態に、
妹・月は顔に火傷を負った。
そんな花のもとに、自分の母の奇病の原因を探る少年・四井 純が訪れる。
やがて純と花は心を通わせていくが、
ある日突然、司朗が5年ぶりに目を覚ました繭子を連れて家に帰って来る。
司朗は“奇跡が起きた”と久々の家族団らんを楽しむが、
花は“あの人はお母さんじゃない”と違和感を覚える。
その時、街では謎の奇病が広がっていた…。
カメラマンとカラリスト、10回目のタッグで臨んだのは“世にも奇妙な謎解きサスペンス”
山下哲司(以下、山下):花村さん、今日はありがとうございます。
映画、公開となりましたね。評判がとても良いみたいで、素晴らしい映画の制作に携わることができて光栄です。
花村也寸志(以下、花村):2015年に公開された映画『ビリギャル』で初めて山下さんとお仕事をさせてもらってから頻繁にカラーグレーディングをお願いするようになり『この子は邪悪』が10作目となりました。
すっかり頼りきっていて今回もスムーズに進んだので、こういう場であえて話すことがないような気も…(笑)
山下:たしかに(笑)
しかし10作目とは感慨深いですね。本作は大括りにジャンルで分けるとサスペンスになると思いますが、以前ご一緒した『事故物件 恐い間取り』ともまた違った独特の世界観でしたね。
花村:そうですね。
ホラー的な要素はあるものの、あくまでストーリーが主体の“謎解きサスペンス”なので、映像で刺激を誘うような見せ方はあまりしたくないなと。
山下:むしろ、とても落ち着いたルックに仕上がりましたよね。

花村:これは山下さんに話したかどうか忘れちゃいましたが、クランクイン前の準備中に映画館でダニエル・シュミットの『ヘカテ』が4K上映されていたのを観たんです。その映像がとても良くて、少し参考にしました。
役者さんの顔に影が落ちている感じとか…特殊な効果ではなく、陰影でキャラクターの感情を表現するために、照明の永田さんには頑張ってもらいました。

山下:『へカテ』の話は聞いてなかったかもしれません(笑)
でも、クランクイン前のテスト撮影の段階で打ち合わせをしたときに方向性は掴めました。
実際に現場で当てて見てもらっていたLUT※をベースに、そこから、強い色はなるべく主張を抑えようとか、黒もギリギリマットに見えるかな、くらいのトーンにしようとか、調整していって。
あのときは劇中で花の妹がつける仮面のパターンを細かくテストされていましたよね。
※LUT:(ルックアップテーブル)の略で映像の色を調整した情報を保持・適用できるプリセット
花村:そうでしたね。本編のなかでもいくつかの仮面をつけ替えるんですけど、監督がどのシーンでどれを使おうか悩んでいたので、スクリーン上こういうふうに映りますみたいなプレゼンをしつつ、シーンごとに使う仮面を決めていく行程でした。
山下:仮面も含め、本作では美術やロケーションが効果的に物語を際立たせている印象があります。首都圏の都市から離れた、ひっそりと佇む街の日常的な景色のなかに、不気味な状況が溶け込んでいる“自然な気持ち悪さ”…その起点となるのが、窪司朗(玉木宏)の心理療法室ですね。
花村:登場する診療室は、木更津にある今は使われていない眼科をお借りしたものです。
しかし、当初は静岡の別の建物をロケハンしていました。その場所も診療室でしたが、表から見ると洋風な佇まいで、奥に日本家屋がつながっているという独特な作りだったんです。
そこで撮影する予定で進めていたところ、コロナ禍の影響で使えなくなってしまい、それでも世界観だけは残したかったので、急遽、診療室は木更津で、窪家が暮らす日本家屋は埼玉で撮影することになりました。


山下:別の場所での撮影となると光の感じも変わりますから、それをマッチングさせるために照明もかなり気を遣ったのでしょうね。
現場で計算されて撮影されていたので、グレーディングでは軽く補正する程度であまり意識せずに済みました。
“曖昧さ”と”説得力”を両立するアナモレンズ。その力を信じた
山下:今回はアナモフィックレンズを使ったことが、映像の世界観を作り出すうえで重要なポイントになりましたよね。
花村:監督が初めからシネマスコープで撮りたいと言っていて、だったらアナモレンズがいいとリクエストしました。
機材費が膨らむので普段なかなか使えないんですけど、無理を言ってお願いしてほぼ全編アナモレンズで撮影したんです。ファーストカットは当初、ドローンで舞台となる街全体が見えるように撮る想定でしたが、せっかく全編アナモだからドローンは嫌だなあと…。
監督に提案をして、ロケ地にあるプールの水面をジブで映すというカットに変更させてもらいました。
実際に撮ってみたらアナモレンズって本当に魅力的で。普段は結構いろいろとフィルターを入れたりするんですけど、そうするとレンズの良さが消えちゃうねって山下さんが言ってくれて、フィルターもあまりかまさずに勝負しました。

山下:アナモレンズを通して見えてくる映像の説得力は、ちょっとかけがえのないものがありますよね。ピントが合っているところと合っていないところの曖昧さとか。エッジ感、フォーカス感、光の滲み方など、いろんな意味で“丸み”があって、どことなくフィルムの頃を思い出す感覚。
グレーディングではアナモレンズの独特の雰囲気を生かし、硬さがありながらもシャープになりすぎないように意識しました。
花村:僕もまさにフィルム的な映像を目指したいという気持ちがあります。
山下:これまでの作品もそうでしたが、2人で「ああだね、こうだね」とやりとりを続けていくと、結局フィルムっぽいところに落ち着きますよね。
花村:そうですね。とはいえ「フィルムっぽい」の捉え方も人それぞれで、憧れがあってもそれを魅力的に表現することは簡単ではありません。以前、別の作品でフィルムLUTを使って最初にテストをしたら、みんな口を揃えて「主演が可愛くなくなってる」と…(笑)
山下さんに相談して修正してもらったところ、満場一致でこれでいこうとなって、そこで山下さんが解釈する「フィルムっぽさ」の正解を見せてもらった気がしました。
お蔵入りになるような挑戦も2人ならできる
山下:アナモレンズの魅力を生かしてシンプルに映像をつくろうと考える一方で、いろいろな“挑戦”もしましたよね。現場からあがってきた映像を見たときは、特に照明の使い方が印象的でした。
花村:いつも一緒に映画を撮っている照明の永田さんが、結構色で遊ぶんですよ。落ち着かないんですよね、永田さんの照明(笑)
というのは冗談で…1つのライトにいろんなフィルターを貼って色を混ぜるとか、いろいろ仕掛けで新しい画づくりに挑戦する人なんです。
今回は窪司朗(玉木宏)が催眠をかけるシーンで、不穏な雰囲気を演出するためにライトをジブに乗せて動かしたりしてみました。
山下:グレーディングでも、別のシーンで、怪しい音楽が流れ出すのをきっかけに部屋のステンドグラスのようなものの色がだんだん強まっていくという特殊な処理を施しましたよね。変化する前と後で比較するとすごく変わってるんですけど、長回しなので観ている人はなかなか気付かないかもしれません。
通常だと、長回しで役者さんが明るい場所から暗い場所に移動したときなどに若干明るさを補正するといったことはありますが、今回のように演出効果的なグレーディングは珍しく、印象に残っています。
照明でもグレーディングでもチャレンジングなことをさせてもらった作品でしたが、監督としてはそのあたりは、花村さんに一任されている感じですか?

花村:映像に関する部分はかなり任せていただいていて、いろいろなアイデアを柔軟に採用してくれました。ストーリーやキャラクターがブレなければ大丈夫だと思っているタイプの方で、逆にその辺のこだわりは強くて結構頑固です(笑)
ただ、回想シーンのグレーディングで、作品のフックになるように“刺激的”なルックにして提案したところ、それは嫌だと弾かれましたよね…。
山下:そうでしたね(笑)昔のVHSを彷彿とさせる、エッジをカリカリにして解像度も落としたルック。アナモで撮影した映像をあえて…。
花村:せっかくよく撮ってくれたのに、もったいない。としっかり拒否され、お蔵入りになりました(笑)最終的にできたものを観てみると、監督が否定した意図もよくわかり、納得のいく仕上がりになりましたけどね。
山下:今までにも、花村さんと僕との間で挑戦して、世には出てないことって結構ありますよね(笑)グレーディングの最終日の夜から全編色を作り直したこともありましたし、いろんな壁を超えてきました。
花村:いろいろありましたね。そんなチャレンジも、信頼できる山下さんとだからできてきたのかもしれません。
きれいに整えることで大切なものが失われるならそのままでいい
花村:山下さんと出会ってから、グレーディングを通して映像の「色」について学ぶようになりましたが、その前は本当によくわかっていなくて。初めてビリギャルでご一緒したときは、とりあえず山下さんが言うことにすべて「NO」と答えようと考えていました。

山下:えー!(爆笑)
花村:逆張りが過ぎましたね(笑)
グレーディング界で長きに渡って活躍する山下さんの作りやすいように任せると、それまでの日本映画を超えられないんじゃないかと。
そのときはこんなに継続してお付き合いするとも思っていませんでしたから(笑)
目の前にある作品を自分なりに良くしたいという思いで必死でした。
山下:そんなスタンスだったとは…「NO」と言われたことはそんなに覚えていませんが(笑)
ただ、花村さんが「映像をきれいに整え過ぎてしまうことの弊害」みたいな話をされた記憶があって、その言葉がずっと僕の心に残っています。

花村:揃ってなくてもいいんだ、みたいな話、したかもしれません。
山下:カラリストの仕事として、さまざまなカットを繋いだ映像を違和感なくスムーズに観られるように整えるという側面があります。しかし、それこそ『へカテ』のように、旧作のフィルム映画などを観ると、カットによって色調が多少バラついていても、かえってそこに現場でみなぎる力強さがしっかりと映像に現れていて、それがそのまま作品の魅力になっている。むしろ、多少バラバラであることによる“引っ掛かり”があってもいいんじゃないかと。
花村:今の撮影・編集技術だときれいに整えることって簡単じゃないですか。撮影した後で、「この赤色をもっとこうしたい」と、その色だけを抜いて補正することもできてしまう。本来であれば映像全体のバランスのなかで、その赤がどう見えるかを考えるべきなんですけど。補正が前提になってくると、現場で自分は何撮ってるんだろうとわからなくなってしまうと思う。
今作で、花(南沙良)と純(大西流星)が待ち合わせをしていて、純が来ないみたいなシーンが2カットだけあって、それがすごくよく撮れたんです。
時間帯や陽の当たり方が絶妙で。そのシーンだけは、あまりいじらないで欲しいと山下さんに伝えました。グレーディングで良くなるかもしれないけど、何か大事なものがなくなってしまう気もして。
そんなことを率直にお願いできるのも、山下さんだからこそだったと思います。

山下:映像に正解はなく、カラリストによって考え方もさまざまなので、より良くするために思いきって画を変えるという考えもあります。
僕はもともとフィルムタイミング出身なので、撮影した生の映像がもつ力を信じ、それに寄り添いたいという想いが根幹にあります。
そういう意味でも、花村さんのように魅力的な映像を映し出すカメラマンと一緒にお仕事ができることは、カラリストとして大きな喜びです。
特に今作ではアナモレンズの力を最大限に生かした映像に仕上がったと思います。
ぜひ多くの方に観て欲しいですね。


映画『この子は邪悪』新宿バルト9ほか大ヒット上映中
出演:南沙良/大西流星(なにわ男子) 桜井ユキ/玉木宏
監督・脚本:片岡翔
主題歌:ゲスの極み乙女「悪夢のおまけ」(TACO RECORDS / WARNER MUSIC JAPAN)
製作幹事:カルチュア・エンタテインメント
制作プロダクション:C&I エンタテインメント Lamp.
配給:ハピネットファントム・スタジオ
TSUTAYA CREATORS’ PROGRAM FILM 2017 準グランプリ作品企画
Ⓒ2022「この子は邪悪」製作委員会
PG12
https://happinet-phantom.com/konokohajyaaku
https://twitter.com/konokohajyaaku
https://www.instagram.com/konokohajyaaku
https://www.tiktok.com/@konokohajyaaku
#この子は邪悪